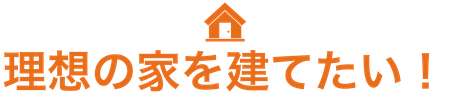注文住宅を建てる際、忘れてはならないのが税金です。
予算にきちんと組み込んでおかないと、最終的な支払いの段階で思わぬ出費に嘆くことになります。
印紙税とは
印紙税とは契約を交わす時に、契約書の記載金額に応じて課せられる税金です。
- 家を買うときは売主と「不動産売買契約書」を交わす
- 家を建てるときやリフォームするときは施工会社と「建設工事請負契約書」を交わす
- 住宅ローンを借りるときは金融機関と「金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)」を交わす
郵便局やコンビニなどで「収入印紙」と呼ばれる切手のようなものを購入し、契約書に貼り、それを消印することで納付が完了します。
家を買うときや建てるときの契約書には減税措置がとられていますが、住宅ローンの契約書では本則税率がかかります。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される契約書の場合の印紙税は次の通りです。
| 契約金額 | 本則税率 (住宅ローン) |
軽減税率 (家の購入・建築) |
|---|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
登録免許税とは
土地や建物を購入する際、通常は引き渡しを受けるのと同時に「登記」の申請を行います。
土地売買の登記には「所有権移転登記」を、新築住宅の登記には「所有権保存登記」を行い、その際にかかる税金が登録免許税です。
登録免許税は登記を行う際に支払い、固定資産税評価額に所定の税率を乗じて金額を決定します。
新築住宅の場合は軽減税率が適用されますが、床面積が50平方メートル以上の長期優良住宅の場合、さらに軽減税率が適用されます。
| 土地 | 税率 |
|---|---|
| 所有権移転登記(土地) | 2.00% |
| 建物 | 税率 |
| 所有権保存登記(通常の場合) | 0.40% |
| 所有権保存登記(新築住宅) | 0.15% |
| 所有権保存登記(認定長期優良住宅) | 0.10% |
住宅ローンを組む際、金融機関はその住宅を担保として抵当権を設定します。
その「抵当権設定登記」については、借入額に応じて税率を乗じます。
| 住宅ローン | 税率 |
|---|---|
| 抵当権設定登記 | 0.10% |
登記は司法書士が行うため、その司法書士への報酬も購入者の負担となります。
消費税
家を建てたり、購入したりする場合、土地は非課税ですが、建物には消費税がかかります。
不動産取得税とは
売買や贈与で不動産を取得したり、新築や増築した際に都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけ支払う税金になります。
固定資産税評価額に対して、原則として税率4%を乗じた金額が税額となり、新築でまだ固定資産税評価額がついていない場合は、都道府県知事が標準額に基づいて評価額を計算します。
特例により、2021年3月31日までは土地および建物は税率が3%に減税されます。
また認定長期優良住宅の場合、控除額が1,300万円に引き上げられるので、さらに減税となります。
固定資産税とは
毎年、1月1日の時点で土地や建物を所有している人が納める税金です。
つまり注文住宅を建ててからは、毎年かかってくる税金です。
一年に一度、納付書が送付されてきますので、納税通知書に従って指定の金融機関に支払います。
固定資産税は、固定資産税評価額に基づいて算出され、税率は1.4%ですので、大体の金額を事前に把握することができます。
固定資産税評価額は3年に一度見直され、それに伴い、支払額も変更になります。
また住宅用地と新築住宅の建物に対しては、軽減の特例が設けられています。
詳細は地域の市役所や依頼しているハウスメーカーなどに確認してください。
都市計画税とは
固定資産税と連動しているのが都市計画税です。
都市計画税も固定資産税評価額に基づいて算出されます。
都市計画税の最高税率は0.3%ですが、市区町村で税率は異なります。
都市計画法に基づいて、市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となり、道路や公園など、市区町村の土地区画整理を行う際に使われる税金です。
市街化区域内の家を所有する場合は、固定資産税と都市計画税が一緒に徴収されます。
注文住宅を建てる際にかかる税金まとめ
減税措置の多くは自動的に適用されるわけではなく、自ら手続きを行う必要があるので、適用されるものは忘れずに手続きしてください。
また認定長期優良住宅の場合、一般住宅よりも大きく減税されます。
もちろん建物価格は高くなりますが、機能性に優れ、減税措置の優遇もあるので、一般住宅よりランニングコストがかからない場合も多いです。
税金の確認をしつつ、20年、30年と長い視野で検討した際に、どの方法が一番おトクになるのか考えながら注文住宅のプランを立ててください。